それは南からの風に夏の匂いが混ざり始めた、とある日のことだった。
世界は瑞々しい新緑に彩られ、春の女神も旅立ちの準備を始めたであろう、暖かく晴れた日のことだった。
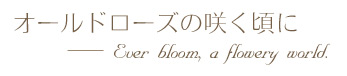
三十年前の消印が押された一通の手紙が、その日、クリスティーナ夫人の元に届けられた。
小さな田舎町の郊外に佇む、一軒の屋敷。いつもなら玄関先のポストに郵便物を届けるとすぐに踵を返してしまう配達員の青年が、その日は珍しく屋敷の鐘を鳴らしたのである。
どうすればあの恥ずかしがり屋の青年が、配達の途中に一杯の紅茶を飲んで行ってくれるのだろうか。夫と紅茶を飲みながら、その難問に適切な答えを見出すべくあれこれと知恵を巡らせていた高齢の夫人は、扉の向こうに件の青年がいたことにまず驚き、そして、届けられた手紙に更に驚いたのだった。
そんなクリスティーナの前で、夫妻にとっては自分達の子供と同じ年くらいの青年は、申し訳なさそうに何度も何度も頭を下げて、その理由を事細かに説明した。
曰く、何かの弾みに仕分けをしそびれたまま、宛て先不明の郵便物として倉庫の奥に眠っていたのが、つい先日発見されたのだそうだ。
きちんとした宛て先が書いてあったにもかかわらず、宛て先不明のまま三十年――田舎の郵便局では局員一同が茶を吹き出すくらいで済んだのだが、大都会にある郵便局だったなら、それこそ新聞の記事にでもなってしまいそうな事件だった。
新聞に載るか載らないかはこの際大した問題ではない。何が起こっても大概のんびりと構えている局長が、その時ばかりは何を差し置いてでも届けろと血相を変えて怒鳴ったものだから、今日配達する予定だった郵便物の確認もしないままに青年は飛び出した。
そこまではまだ良かったのだが、何しろ日付は三十年前のものである。宛て先として記されていた住所が示す場所自体は辛うじて残ってはいたものの、そこに住んでいたのは当然の如く赤の他人だった。
少し冷静になって考えてみれば、その現実に思い当たるのもさほど難しいことではなかったのだが、とにかく飛び出した瞬間はそれどころではなかったのだろう。配達員の青年は我に返ると、手紙を握り締めたまま途方に暮れてしまったらしい。
けれども、そこを偶然通りかかった夫人の旧い友人であるという女性が、夫人が結婚と共に引っ越した先の住所を教えてくれたために、こうしてようやく届けることが出来るに至ったと言うのである。
何度もこの家に郵便物を届けに来ていた青年も、さすがに夫人の旧姓までは知らなかったようだ。クリスティーナというファーストネームを持つ女性はこの大陸だけでも数え切れないほどいるだろうから、無理もない。
間違いありませんかという青年の問いかけに、クリスティーナは、驚いたような嬉しそうな、何とも言えない曖昧な表情を浮かべて頷き、その封筒を受け取った。
元は白かったのだろうそれは長い年月の間にすっかり変色しており、表面のインクの色も心なしか褪せてしまっていた。それでも、綴られている文字そのものは十分に読み取ることが出来る。
三十年前に届けられるはずだった宛て先は隣町のもので、クリスティーナが結婚する前に住んでいた家のそれに間違いなかった。
宛て名は“Christina・Klein”――クラインは紛れもなく、夫人の旧姓である。
クリスティーナは震える手でその封筒を裏返した。三十年の歳月を経てもしっかりと封がされていて、その証として、麦の穂と角のある馬がかたどられた封蝋が押されていた。
差出人の名と思しきものはどこにも記されていなかったが、クリスティーナは一目でその手紙の主が誰であるのかを知った。
「ああ、ロビン……あなたなのね……」
愛しそうに、懐かしそうに、クリスティーナはゆっくりとその名を紡いだ。そうして、やはり丁重に紅茶を断り去って行った配達員の青年を見送ってから、部屋に戻るまでの時間さえ惜しかったのか、その場で封を開ける。
入っていたのは、丁寧に折り畳まれた便箋が一枚。
クリスティーナは逸る気持ちを抑えながら、彼女へと宛てられた三十年越しの手紙を広げた。
Dear,Christina――
君の側を離れてから、二度目の春がやってきた。
君は、元気にしているだろうか。
取りあえず僕は、こうして手紙を書けるほどには元気にしているよ。
手紙を送ると言ってから、こんなにも時間が流れてしまったのは、
それだけ机に向かう暇もなかったのだと、そう思って頂ければ幸いかな。
もちろん、笑ってくれても構わない。けれど、どうか怒らないでやって欲しい。
僕は君の怒った顔も好きだけれど、笑った顔の方がもっと好きだから。
――――……ああ、困ったな。暫くペンを握らなかった間に、
どうやら僕は字の書き方すらも忘れてしまったらしい。
言いたいことも書きたいこともたくさんあるというのに、
いざ紙とペンを目の前にすると、何も言葉が出てこないんだ。
クリスティーナ、早く君に逢いたい。早くこの手で君を抱き締めたい。
元気にしているだろうか。こればかりが今は気がかりだ。
国境付近も、だいぶ落ち着いてきた。
もうすぐ戦争は終わると皆は言っているけれど、どうやら本当のことらしい。
そろそろ、君が焼くチェリーパイの味も恋しくなってきた。
だから、あと一つ季節が巡ったら……
カメリアベリーが美味しい季節になったら、きっと君の元へ帰るよ。
どうか、それまで待っていて欲しい。必ず、君の元へ帰るから。
こっちでは、君の大好きなオールドローズが、とても綺麗に咲いている。
そっちでも、もうすぐ咲くだろうと思う。
さすがに花そのものを手紙に添えることは出来ないけれど、
せめてこの、ローウェンブルクの春の香りだけでも一緒に届くことを願って。
この二年で、帰る場所があるということの心強さを何度も実感した。
君の笑顔や声を、色々なものをひっくるめて、『君』を忘れずにいられたから、
こうして僕は、この地で生きてこられたのかもしれないとさえ、今は思う。
だからこそ、僕はこの言葉を君に贈ろう。
愛するクリスティーナ、君に逢えてよかった。
僕の心は、いつでも君と共に。
少し早いかもしれないけれど、十九歳の誕生日、おめでとう。
君の側を離れてから、二度目の春がやってきた。
君は、元気にしているだろうか。
取りあえず僕は、こうして手紙を書けるほどには元気にしているよ。
手紙を送ると言ってから、こんなにも時間が流れてしまったのは、
それだけ机に向かう暇もなかったのだと、そう思って頂ければ幸いかな。
もちろん、笑ってくれても構わない。けれど、どうか怒らないでやって欲しい。
僕は君の怒った顔も好きだけれど、笑った顔の方がもっと好きだから。
――――……ああ、困ったな。暫くペンを握らなかった間に、
どうやら僕は字の書き方すらも忘れてしまったらしい。
言いたいことも書きたいこともたくさんあるというのに、
いざ紙とペンを目の前にすると、何も言葉が出てこないんだ。
クリスティーナ、早く君に逢いたい。早くこの手で君を抱き締めたい。
元気にしているだろうか。こればかりが今は気がかりだ。
国境付近も、だいぶ落ち着いてきた。
もうすぐ戦争は終わると皆は言っているけれど、どうやら本当のことらしい。
そろそろ、君が焼くチェリーパイの味も恋しくなってきた。
だから、あと一つ季節が巡ったら……
カメリアベリーが美味しい季節になったら、きっと君の元へ帰るよ。
どうか、それまで待っていて欲しい。必ず、君の元へ帰るから。
こっちでは、君の大好きなオールドローズが、とても綺麗に咲いている。
そっちでも、もうすぐ咲くだろうと思う。
さすがに花そのものを手紙に添えることは出来ないけれど、
せめてこの、ローウェンブルクの春の香りだけでも一緒に届くことを願って。
この二年で、帰る場所があるということの心強さを何度も実感した。
君の笑顔や声を、色々なものをひっくるめて、『君』を忘れずにいられたから、
こうして僕は、この地で生きてこられたのかもしれないとさえ、今は思う。
だからこそ、僕はこの言葉を君に贈ろう。
愛するクリスティーナ、君に逢えてよかった。
僕の心は、いつでも君と共に。
少し早いかもしれないけれど、十九歳の誕生日、おめでとう。
22th Aprilis 1822
Robin・Fluorite
Robin・Fluorite
手紙を読みながら、クリスティーナは堪え切れなかった涙を何度も手で拭った。そして、何よりも彼の純粋な想いを、何度も何度も読み返した。所々に書いた文字を消した跡がうかがえるのは、それだけ戦場において紙が希少品だったということの表れだろう。
たった一枚の、色褪せた紙切れに過ぎないようなそれに綴られた、無骨だけれど丁寧な文字。手紙に記されていた日付も――消印よりもさらに半月ほど前のものであったが、やはり三十年前のものだった。
大陸中で争いの火種が絶えなかったのは、三十年以上も前――クリスティーナが、まだ若かった頃の話だ。幸いにも、クリスティーナやロビンが住んでいたこの辺りは戦火に遭うことはなかったが、周辺に点在する多くの国や町が戦場となり、数え切れないほどの人々が命を落としたと言われている。
誰が正義で誰が悪とも言えない、そもそも発端がどこだったのかさえわからない、そんな終わりの見えない戦争に多くの者達が駆り出され――そのまま帰らなかった者も、決して少なくはなかった。クリスティーナの婚約者であったロビンだけでなく、クリスティーナの父や兄達、ロビンの父親、そして彼らの友人や同輩なども、ロビンと同じく戦地へと赴いたのだった。
この手紙は、その戦場からやっと出来た暇を用いて出されたものだったのだろう。体を休めるための大切な時間を、彼は、わざわざこの手紙に割いてくれたのだ。
クリスティーナは静かに手紙を抱き締めた。気の遠くなるような時間を越えてやっと届けられた、たった一枚の便箋――それに綴られた若き日のロビンの想いを抱き締めながら、クリスティーナは、ただ、笑った。
ふわりと、春の残り香が鼻腔を擽ったような気がした。
この手紙がポストに入れられてからおよそ半年後に、五年に渡って続いた戦争は終わりを迎えた。世界中が傷つき荒れ果てていたが、長い時を経て、その傷跡さえ残らないくらいに復興した。
世界は戦争のことを忘れつつあり、戦争を知らない子供達が今の世界を動かしていると言っても――もはや過言ではない。
そして彼女は今、戦争当時よりもずっと裕福な暮らしを送っている。愛しい夫と三人の子に恵まれ、去年の夏には初孫も生まれた。もうすぐ二人目の孫の顔が見られるという。子供達は全員無事に独立し、今は夫と二人、この郊外の家でのんびりと余生を楽しんでいるのである。
「……まったくもう、あなたが待ち合わせに遅刻するのは昔から変わらないと思っていたけれど、まさか、三十年も遅れて来るとは思っていなかったわ……」
そう、デートの待ち合わせにだって彼はいつも遅れてきたのだから、手紙が届くのが遅れたって不思議ではない。笑いながら呟いて、クリスティーナは空を見上げた。ロビンが戦場へと向かったあの日もこうして空を見ていたことを、今更ながらに思い出す。
あの時も、空は今と変わらずに青かった。どこまでも続く空を、大きな白い雲が流れていた。沈む夕日も昇る朝日もこれ以上はないというくらいに美しかったし、あの頃も今も変わらず、世界は輝いている。
戦火にいつ呑まれるともわからない日々を送りながら、しかし、そのことで絶望を感じたことなどなかった。
何よりも、ただその日その日を生きられる――そのことにばかり感謝した。
彼が戦場に赴く前に、最後のデートをした日。昔住んでいたあの町の近くにある、オールドローズが咲き乱れる森。あの場所で、彼は二つの約束をクリスティーナに託した。
『必ずここに帰る。それから、結婚しよう』
その時クリスティーナは、彼から、銀色に輝く指輪を受け取った。左手の薬指に嵌められたその指輪は、彼が戦場に赴いてからも彼女の心の大きな支えとなった。
空が繋がっているならきっとこの願いも届くだろうと、彼の無事を信じて祈り続けた日々があった。
彼が帰ってきたらまず何を言おうと、そんな他愛もないことばかりを考えて眠れない日々が続いた。
彼のためにと上等な布を買い、新しい外套や帽子を眠る暇も惜しんで縫い上げた日があった。
頬が落ちそうなほどに美味しいチェリーパイが焼けたと、母や妹達と手を取り合って喜んだ日があった。
人込みに良く似た後姿を見つけては、帰ってきたのではないかと胸を躍らせたことも―― 一度や二度ではなかった。
忘れかけていた思い出が、この手紙と共に次々に溢れては、クリスティーナの心の琴線を弾いていった。
時間は戻りはしないというのに、心は、若かりしあの頃の自分に戻ってしまったようだった。
「わたしも、あなたに逢えてよかったと思っているのよ、ロビン……だって、だって今、こんなにも幸せなんですもの……」
クリスティーナは細く震える指先で、ゆっくりと綴られた文字をなぞる。
ともすれば、これをしたためていた瞬間の彼の姿さえ思い浮かべることが出来そうだと、クリスティーナは思った。
「……扉を開けたまま何をしているんだい、クリスティーナ……そのままでは、君の体が冷えてしまうよ」
呼び出しの鐘の音に応じて部屋を出たきり戻らなかった彼女を心配したのだろう。ゆっくりとした足取りで階段を下りてくる夫の元に、クリスティーナは泣き笑いにも似たような表情を浮かべ駆け寄った。もちろん、扉を閉めるのも忘れない。
「あら、こんなに暖かいんだもの、大丈夫よ。それより聞いてちょうだい。三十年前のあなたからラブレターが届いたのよ、ロビン。ほら、三十年前のあなたも、今と変わらずとても情熱的よ」
「……は……?」
突然のことに状況が飲み込めなかったのだろう、目を丸くしてその場に立ち尽くしたロビンに、クリスティーナはそっと抱きついた。悪戯っぽく笑みを浮かべて、腕を解き、大きく瞬きを繰り返している夫の目の前に手紙を掲げる。ロビンはそれを両手で大事そうに受け取ると、信じられないと言ったような表情でその文面に目を走らせた。
「これは……僕が君に宛てた手紙か……てっきり火に呑まれてしまったのかと思っていたけれど、よく、今まで残っていたね」
「そうよ、ロビン。こんな素敵な手紙を送ってくれていたなんて、聞いていなかったわよ。届いていないとわかっていたら、すぐにでも探しに行ったのに」
「……ああ……いや、わざわざ探すほどの物でもないと思っていたからね……そうか、やっと君の元に届いたのか……」
三十年前の自分自身との対面を果たし、ロビンはどこか感慨深げにその手紙を眺めやる。寄り添うように彼の手元を覗き込みながら、クリスティーナは、囁くように言った。
「もうすぐカメリアベリーの季節だものね。腕によりをかけてチェリーパイを作るわ。それから、オールドローズを見に行きましょう? ……ノルズウェイのあの森に」
「二人で行くのもいいけれど、そうだね、今度は子供達も呼ぼう。案外、君のチェリーパイの味を恋しがっているかもしれないからね」
「まあ、ロビンったら」
ゆっくりと回されるロビンの腕に、クリスティーナは静かに身を委ねる。
ちょうど三十年前の今頃、この手紙がポストに入れられてから少し後――彼が真っ赤なオールドローズの花束を持って戦場から戻ってきた、その時と同じような勢いこそなかったけれど。
それでも、クリスティーナは全身でしっかりと、愛しい夫の体を抱き締めた。