雨の降る路地裏、打ち捨てられた木箱の上で蹲るように座り込んでいた。襤褸切れでしかない布を被り、靴さえもない足は爪も見えないほど傷だらけで――足だけではなく、体中が汚れ擦り剥けているような、そんな少女だった。
放っておけば明日にでも、《
「……名前は?」
少女は首を横に振った。答えられないのか、覚えていないのか、それすらも判別がつかない。
ともかくも冷えた身体を温め、汚れた身体を洗うのが先だろうかと、そう思って伸ばした手に対する――明らかな怯えの色。
「俺が怖いか?」
少女は答えなかった。ただじっとこちらを見つめ返してくるだけだった。
今度は慎重に、少女を抱き上げるように両腕を伸ばす。少女はぎゅっと両の目を瞑ったが、彼の動きを拒もうとはしなかった。逃げられないと悟ったか、あるいは人攫いと思われたか。いずれにしても少女の心中を推し量ることなどできなかったし、そんな悠長なことを考えている暇もなかった。
ともかくも少女を――見た目よりもずっと軽く感じた小さな身体を抱え上げると、その場を後にする。厄介事に巻き込まれなかったのは幸いだった。
有り合わせの物を煮込んだだけのスープでも、少女の体を温め、声を取り戻させるには十分なものだったようで――食事が終わる頃には、少女は拙い言葉でレヴィーナと名乗った。
レヴィーナはその背に、翼のような痣を持っていた。体の汚れを落としてもそれだけは落とせなかった。生まれつきのものだと、レヴィーナは言った。
その時には追われる身であると言っても過言ではなかったウェイブ=クラウドがその少女を拾ったのは、単なる気紛れでしかないのかもしれなかった。
――あるいは、傷だらけの顔でこちらを見ていた、その眼差しに微かな光を見出したからかもしれなかった。
それから、数年。
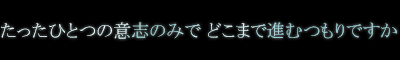
眼前に聳える灰色の壁を見上げて、ウェイブ=クラウドは軽く舌を打った。入り口は硬く閉ざされていて、それを潜ることが許されるのはごく限られた一部の者だけだ。そしてウェイブには、どう足掻いてもその資格を手に入れる手段はない。
《
研究者達にとって楽園とも称されるこの場所は――『実験台』にされる者にとっては、一歩足を踏み入れれば二度と出ることの叶わない檻だと、そんな噂さえまことしやかに囁かれているし、それはある意味真実に等しい。
この世界に星の数よりも多く存在している、いわゆる人智を遥かに超えたもの――それらをすべて明らかにしたいと心躍らせる者が集うのが、この場所なのだから。
彼女はこの壁の向こうにある、檻の中に囚われてしまった。ゲストでも研究者でもなく、『研究対象』という名目の実験台として。
彼女がこの世界においてどんなに希少価値の高い存在かなど、少なくともウェイブにとってはどうでもいい話だ。ただ、ここに連れて行かれるのを黙って見過ごすわけにはいかないほどには、彼はこの場所がどのような場所であるかを理解していた。
そして、彼女のために剣を振るう理由を作れるほどには、彼は彼女と共にいた。
だからこそ彼は、その檻を抉じ開けて彼女を連れ出さなければならない。彼は今、それを何よりも最優先で成し遂げなければならない。
そうしなければ、彼女は好奇心という名の剣で全身を貫かれてしまう。
ウェイブは右耳で揺れる淡い水色の宝石がついたイヤリングに、そっと手で触れた。精霊を宿した石――もう片方のイヤリングは、彼女が持っているはずだ。もちろん、捕らえられた時に取り上げられていなければの話だが。
その宝石よりも鮮やかな瑠璃色の瞳で、空を見上げる。時は夜。《
《
それとも――己と同じ金の髪を持つ女神、《
けれど、彼にとっての女神は――例えるならば彼女だろう。
「……レヴィーナ」
女神の名を呟いて、彼は一歩踏み出した。腰に帯びた一振りの剣、その柄を強く握り締める。
彼女にもしものことがあったら、この庭に集う者全員を斬り捨てることさえ厭わない――そんな決意を両の瞳に宿らせながら、彼は壁を乗り越えるための仮初めの翼を得るべく、風を導く言葉を口にした。
*
すれ違う際に言葉すら交わさない――そんな息苦しい世界に、クロードはどうしても慣れることができなかった。
だから上司であるその男といる時には、どうしても口数が多くなってしまうことも自覚していた。『ここ』がそういう場所だと教えてくれたのは、他でもないその人だ。
基本的に研究者達は己の関心のあることにしか興味を示さない。よって身近な同胞である他者に関心を示さない者も少なくはなく、常に張り詰めた空気に満たされていると言っても過言ではない。
上から下までを覆う亜麻色の長い衣に、小豆色の帽子。同色の靴と手袋。小豆色は博士にのみ許された色で、学士のそれは深い青紫だ。
同じ服に身を包んでいてもそれぞれの顔は違うはずなのに、自分達以外の人間がみんな同じ風に見えたこともあるから、クロードは上司でもあり博士でもあるその男以外の研究者と擦れ違うのさえある意味怖かった。
幸いにも今は、どこまで続くとも知れないその通路を歩いているのは彼らの他にいなかったのだけれど。
「一言で言うなら、空を飛ぶための力であり、そのための羽だと定義付けられている。翼とは違う。文字通り、羽だ。例えるならば……やっぱり羽が一番わかりやすいだろうな。半透明で、色は様々だが……蜻蛉の羽に似ている」
首を傾げるクロードに、レオナルドはやけにあっさりとした口調で告げた。クロードはすぐには理解できなかったらしく、紫紺の瞳にますます疑問の光を宿し、青銀の髪が肩から零れ落ちてしまうくらいに首を傾げるばかりだ。
「背中から生えているということですか? あの――《銀の翼を持つ者》みたいに」
その名を聞いた途端に、レオナルドが顔を引きつらせる。琥珀の瞳を苦虫を噛み潰したように歪めながら、くしゃくしゃと乱暴に金の髪を撫ぜて、脳裏に二つの影を過ぎらせる――それは、レオナルドにとっては思わず苦笑したくなるような存在だった。
「……思い出させてくれるな。苦い記憶しか浮かばん。それに、奴は奴でまた存在そのものが俺達とは違う。奴はどちらかと言うと精霊種に近いが、《黎明の羽》は精霊とも妖精とも違う」
「博士……もしかしてまだ彼から血を貰えなかったこと、根に持ってるんですか?」
クロードは恐る恐る尋ねてみた。禁句かもしれないと思った時には、既にレオナルドの口からは深い溜め息が溢れ出ていた。
「いや、惜しいことをしたとは思ってるが、別に根に持ってるわけでもない。何、再び会う機会はいくらでもあるだろうさ。それに、奴よりは寧ろ連れのお嬢さんだな。可愛い顔して痛かったぞ、さすがに、アレは」
今となってはいい思い出だが、忘れられるはずもなかった。件の《銀の翼を持つ者》は、遥か昔の時代から召喚された、今となっては滅びた一族の末裔だ。そんな彼らの生態が明らかにできれば、レオナルドとしてもクロードとしても、大きな出世のチャンスを掴み取ることに繋がる。そのため、彼らはある意味夢中になって《銀の翼を持つ者》を探していた。
初めての――もしかしたら、最初で最後になるかもしれない邂逅は数ヶ月前。まだ
問題は、彼の連れだという、紅い髪の魔術師の少女だった。
「……《
説得も最初から通じず、怪しい実験に使うに決まっていると決め付けられ、彼らは弁解の余地すら与えられずに、彼女の魔術による手痛い一撃を受けて退散したのであった。
「……話を元に戻しましょうか」
「脱線させたのはお前さんだろうよ。まあ……《黎明の羽》は、人間の中でも突然変異種だというのが、専らの通説だ。有翼種の存在は確認されているが、それともまた違う。簡単に言えば、翼の出し入れができるかどうかだ。賢者ソフィアや古エトルリア人に代表される有翼種は、鳥と似たようなもので骨格がある。つまり背中から直に生えている。ところが、《黎明の羽》はそうじゃない。あれは……魔力を羽に変えるとでも言うんだろうか、そんな感じだ。今までにもいくつか話は聞かれていたが、実際に細かく研究がなされてきたわけじゃない。ここで……彼女が仮に《黎明の羽》の持ち主だとしたら――」
「……だとしたら?」
確認するまでも、先を促すまでもなかった。《黎明の羽》という、未知の存在をその身に宿した娘――研究者達が先を急ぎ、必死になるのは、目に見えて明らかである。答えは至って簡単だ。
「――さあな、彼女はただでは済まんだろう……それしかわからん。所詮俺達はしがない一研究員に過ぎん。後はギルドの管轄だ。徹底的に組織の一つ一つから調べられるかもしれん。だが――クロード、彼女を逃がそうなんて考えは起こさん方が身のためだぞ。ここは《深緑の庭》だ」
人間として扱ってもらえるかどうかさえ確かではない。二人の顔が少々曇ったのは、ほぼ同時だった。この《深緑の庭》に籍を置いている以上、レオナルドもクロードも肩書きは学者であり、研究者である。未知の分野に足を踏み入れ、まだ世間一般に知られていない真実を明らかにするのが彼らの役目だが、罪もない女性を傷つけてまで成果を得ようとは二人とも思っていない。
けれど、すべての研究者がそうであるとは限らない。《深緑の庭》は広い。様々な人間達がいる。中には、同じ人間をも道具としてしか見れないような研究者だっているのだ。彼らの手にかかったら、もう生きては帰れない。命が残ったとしても、二度とそれまでの生活には戻れない。
「でも、彼女がそうでないということも、ありえるんですよね?」
クロードは縋るような思いと眼差しを、レオナルドへと向ける。レオナルドは小さく頷いたものの、それは完全な肯定ではなかった。
「可能性としてはな。ただ……《黎明の羽》を持つ者は、その背に翼のような痣があるそうだ。俺の目に狂いはそれほどないからな、まず間違いはないと見ておいたほうがいい」
「……そんな……!」
――侵入者の存在を告げる鐘の音が鳴り響いたのは、その時だった。広大な敷地内の隅から隅まで駆け抜ける、目覚ましの鐘よりもやかましい音。
続くように響き始めるのは、廊下を駆けるいくつもの足音と、剣がかき鳴らす金属音。
「……姫君の救出に、騎士が乗り込んできたということか」
レオナルドはゆっくりと辺りを見渡しながら、妙に納得したような面持ちでその警鐘を聞いていた。危険が迫っているというのに、落ち着いた――あるいは、楽しそうな笑みが浮かんでしまうのを、どうにも押さえきれない。
「まあ――奴だったら来るだろうな。何せ、彼女にとってはあれは王子だ。似合わないことこの上ないが」
ここはハイゼルセイド王国の膝元にある研究機関、《深緑の庭》だ。内部にいるのは何も研究者達だけではない。王国お抱えの騎士や魔術師だって闊歩しているのだ。一人で乗り込んでくれば、それこそ生きて帰れるかどうかさえ危うい。
それでも、ただ一人の守るべき人の為にここまで来れるような男をレオナルドは知っていた。彼女がいないなら世界など要らないと、そう答えるであろう男を彼は知っていた。その男が来たに違いない、そう思うと、楽しくて笑うことしかできなかった。
「……博士……?」
「クロード。何も、彼女を俺達が逃がそうとする必要はないぞ? 面白いな、こいつは傑作だ。さて……ここまで来ることができるか? ――ウェイブ=クラウド」
ざわついた雰囲気が、《深緑の庭》を満たし始めていた。