どう見ても外部の者にしか見えない男が、警備に当たっている兵士達を次々と切り伏せている。厚いガラスの壁で隔てられているにもかかわらず、剣を交える音がここまで聞こえてくるような気がして、レオナルドはこっそりと溜め息をつきながら眼下に広がる戦場を見ていた。
侵入者の腕が確かなものであることくらい、素人目に見てもわかる。その鮮やかな剣捌きを、ガリテアの闘技場――《クウェルの舞台》で見てみたいと考えてしまうくらいには。
腕を上げたなと胸中で呟いて、レオナルドは小さく首を横に振った。最後に会ってからどれだけの時間が流れたのだろう。
「は、は、博士、そんなのんびり構えていていいんですか!? 扉開いてますよ、あれ!」
クロードが慌てふためくのも無理はなかった。なぜならここは《深緑の庭》――いかなる理由があろうとも、外部からの第三者の侵入は許されないような、そんな場所でなければならないはずだ。少なくとも、この若い見習い研究者にとっては。
「あん? ……誰かが閉め忘れたんだろう、不可抗力だ」
――とは言え、どのような物事にも例外は存在する。それを彼には知っていて欲しいと思う。そんな優しさのつもりでやらかしたことではなかったけれど――軽く視線を泳がせつつ、レオナルドは飄々と言ってのけた。本当にこの青年は不幸な上司に巡りあったものだと、我ながら不遇を案じてしまう。自分のようにどのような状況下にあっても楽しめるくらいの心積もりを持ってもらいたい――寧ろそれくらいの度胸がないと研究者としてやっていけないのではないかとさえ思ってしまうのだが――なかなか、上手くはいかない。
「ふ、不可抗力ってそんな呑気なこと言ってる場合じゃないでしょう、あの人、ウェイブ=クラウドじゃないですか! ……レヴィーナを取り戻しに来たんだ」
そう、彼は目がよく、読解力と想像力に長けているのだ。いい意味でも、悪い意味でも。
「よく見えるな、クロード。確かに、あの男がウェイブ=クラウドなら、目的はそれしかないだろうな」
「……殺されちゃいますよ、僕達」
「お前は奴を知らんからな、何、そこまで物騒な男じゃない。クロード、そんなに引っ張らなくともお前さんが驚いているのはよくわかる」
縋りつくように袖を引いてくるクロードの手を、レオナルドは素っ気無く振り払った。いつものことだし彼の気持ちもわからないでもないが、こんなつまらない行為で服を駄目にされるわけにもいかない。制服は支給品の一つとは言え、使い捨てのように買い換えられるほど安くもないのだ。
「け、警備の兵士達がまるで歯が立たないなんて、こんなことが……」
クロードが肩を震わせ、息を飲む音が聞こえた。そう言えば機会がなかったので問うことはなかったが、『彼』にまつわる事実を、この年若い青年は果たしてどこまで知っているのだろう。
「クロード。お前さんは……奴のことをどんな風に聞いている?」
ふと浮かんだ疑問をそのまま言葉にしてみると、案の定、クロードは首を捻って考え込んだ。
「――荒野の氷剣……ええと、蒼穹に煌く緋色の漣、戦場を飛ぶ……竜巻のような、と。彼が駆け抜けた後には、切り裂かれた屍しか残らない……みたいな」
「……当人が聞いたら硬直しそうだな」
その記憶の糸が手繰り寄せた『通り名』に、レオナルドは眉を寄せる。誰がそう呼んだのかは知らないが、自分だったらご免被りたいと思わずにはいられない響きだ。だが求めていた結論はそれではないから、こめかみの辺りをほぐしながら気を取り直す。
「いいか、クロード。噂には羽根がつく。目に見えるものを真実だと思え。ウェイブ=クラウドという男を、お前さんはこれから目の当たりにするかもしれん。お前さんが信じるか信じないかはまた別の問題だが、少なくともお前さんが噂に聞いている男とは違うはずだ」
「つまり、彼が『ここ』に来るってことですか?」
「奴の友人はそう多くはないからな、この場所で一番に頼られる自信はある」
「えっ、僕そういうつもりで言ったんじゃ……あっ!」
反論しかけて見るからに青ざめたクロードの、その視線を追いかけるようにレオナルドはちらりと振り返る。
「――フェル」
それを待っていたようなタイミングで、聞き覚えのある声が己の名を呼んだ。フェライーダという名をそう呼ぶことを許した相手は、レオナルドの記憶の中に二人しかいない。
予想通りの展開に、レオナルドは今日だけで何度目かになるかわからない溜め息を、閉ざされた庭の一角に溶かした。こうやって人知れず蓄積された彼の溜め息で、いつか《深緑の庭》中の研究員が憂鬱な気分で一日くらい過ごすことになったりしたらそれはそれで大層面白いのだろうと彼は常々考えているのであるが、さすがに今回ばかりはそんな遊び心を泳がせるわけにもいかなかった。この来客に冗談や遊び心はあまり通じない。
「クロード、良かったな。謝るなら今の内だぞ」
「えっ、そ、そんなこと言わないで下さいよ、博士……!」
どうやら『彼』は、《深緑の庭》の中扉を越えてから真っ直ぐにここを目指してきたらしい。自分達がここにいることを見られていたようだ――レオナルドは侵入者たる男を目の前にして、色々な意味で呑気な思考を巡らせるが、どれもこれも気晴らしになりそうにはなかった。
「久しぶりだな、ウェイブ=クラウド。茶の一杯でも出してやりたい所だが、お前さんの好きなラプラスの茶葉はちょうど切らしていてな」
「……レヴィーナはどこにいる」
物騒な男ではないとレオナルドが評した相手は、こちらに対し、どう見ても問答無用で剣を突きつけてきている。
それは、再会を祝う友人同士のやり取りにはとても見えない。
「それが久方振りに会った親友にものを聞く態度か」
「あんたと親友になった覚えはない」
「……変わっていないな、相変わらずだ」
――その時、クロードは本気で死を覚悟したという。
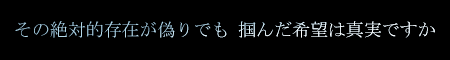
例えばここに一通の封筒が置いてあって、そこに『レヴィーナへ』なんて書かれてあったら間違いなく自分の出番なのだけれど、最大の問題はその字が読めるかどうかということに気づいてしまってレヴィーナは残念そうに溜め息をついた。
自分の名前をどんな字で書くのか、それはウェイブが教えてくれた。だが、この部屋の主だという人はウェイブが教えてくれたものよりもずっと難しい言葉を知っているのだろう。
だってそう、本棚に並んでいる文字だけでもうちんぷんかんぷんだ。
「黎明の、羽」
まるで呪文のように、レヴィーナは呟く。《レイメイノハネ》はとにかく希少価値の高いものらしい。持っているだけですごいのだとか、そんなことを言われても何が『とにかく』で『すごい』のか、やっぱりわからない。持っているのはレヴィーナなのかもしれないのだから、その《黎明の羽》についてもう少し教えてくれてもいいのに。
だからこその、あの莫大な身代金だったのかと、レヴィーナは今更ながらに思い描いてようやく納得した。こんな結論に辿りつくまでにたくさんの回り道をしたような気がしないでもない。
あげられるものなら多分誰かにあげている。それができないからこそここにいるのだとわかっていたが――誰か羽だけ持って行ってくれたりはしないのだろうか。そうすればレヴィーナが家に帰ったって文句は言われないだろうに――と、決して叶わないと言っても過言ではなさそうな望みを抱いて、レヴィーナは溜め息をついた。
「そうだ……帰らなくちゃ」
きっとウェイブが待っている。あのお金に化けてしまったのだと言ってもウェイブは信じたりはしない。早く元気な姿を見せてあげないと、怒って家に鍵をかけてしまうかもしれない。それを開けるのはレヴィーナにとって楽しみの一つだったが、彼の機嫌を損ねてしまうのは本意ではない。
――だから、帰らなければ。
鏡の前でちょっとくしゃくしゃになった髪の毛を整えてみたりしてから、レヴィーナは決意も新たに頷いた。
大丈夫、帰れる。帰り道はわからないけれどきっと何とかなる。鏡に映る自分もそう言っている。
そして、先程から勝ち目のない睨めっこを繰り返していた扉の前に立つ。
どこからどう見ても少し豪華であること以外には特に変哲のないただの扉であったが、どこまでも大きく聳えているように見えて、レヴィーナは少し怖いと思った。
けれど、合言葉も知らないし鍵を開ける道具も持っていないから、力ずくで開けるしかない。誰かが開けてくれるのを待っている時間はないし、もし開けてくれる誰かがいるとすれば、それはレヴィーナの味方でないことは明らかだ。
レヴィーナは大丈夫と心の中で何度も何度も呟いて、扉についていた飾りのようなノブを握り締めた。それを力任せに捻りながら、壁のような扉を押す。ここから出るためには例え壊れてしまっても構わない――寧ろ壊してでも外に出るつもりで――全身でぶつかる。
無機質な扉の確かな手応え。一度ぶつかったくらいでは開かないと、そう思っていたのだが――
「……え……っ!」
しかし、耳に届いた音は思ったよりも大きくはなかった。悪戯な風が足を出して待っていたと気づく間もなく、扉に向けた力がそのまま全身に返ってきたような衝撃を受けて床に転がる。驚きの後に、苦い痺れにも似た鈍い痛み。
「うそ……」
静寂が満ちていた廊下に、彼女の小さな疑問の呟きがぽつりと落ちた。間どころか腰が抜けてしまったような表情で、ぐるりと辺りを見渡す。
――扉には、鍵がかかっていなかった。
前方に広がっているのは、まだ見ぬ世界といっても過言ではない広大な《庭》の一角。振り返れば先程まで彼女が退屈を撒き散らしていた部屋があるだけだ。誰かが隠れているわけでもない。可能性があったとすれば、彼女がこの部屋に訪れたその瞬間から既にそうだったのだと思わざるを得ない。
レヴィーナは立ち上がり、最初の一歩を力強く踏み出した。
単なる気紛れか、偶然という名の幸運か、それとも罠か。外に出られるのなら、どれでも構わなかった。