あの日の雨はとても冷たかった。まるで《
温かくもなければ優しくもなくて、いくつ貰ったって少しも嬉しくないのに、レヴィーナはそれを避ける方法を知らなかった。
きっと、もう二度と明日の朝の光を見ることはできないのだろうと、あの時はそう思っていた。
けれど、そんな彼女の前に彼は現れた。夜の空の色の瞳に、彼女の姿がはっきりと映っていた。
――星が降ってきたのだと、思った。
あの星の輝きを、レヴィーナは片時も忘れたことはない。
忘れられるはずなどなかった。それほどまでに綺麗だった。
まるで心の中に降り注いだみたいに。
まるで、行く先を照らしてくれたかのように。
この星の輝きを追いかけていけば大丈夫だと、その時、レヴィーナは誰に言われるでもなくそう思った。
そして、それは本当だった。彼女が今もこうして生きているのは、彼が側にいてくれたからだ。
食べる物があり、眠る場所がある。風や雨の冷たさに怯えることもない、あたたかい場所だ。
ウェイブはどうして自分を助けてくれて、今も側にいてくれるのだろう。
その理由を、聞いてみてもいいのだろうか。聞いたら、答えてくれるだろうか。
これからもずっと一緒にいたいと言ったら、彼はそれを許してくれるだろうか。
聞いてみよう。帰ったら。
きっとあのウェイブのことだから、恥ずかしくて答えられなくて黙り込んでしまうに違いないけれど。
だから、生きて帰らなければ。
雨が降る空の下よりずっとずっとあたたかい、あの家へ。
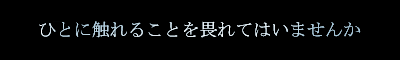
「……どこ、かな。ここ」
どこまでもどこまでも入り組んだ迷宮。レヴィーナは自分が今どこにいるのかまったくわからなかった。
天井を見上げても通路の向こうを見つめても、同じような空間がずっと続いているばかりなのである。
規則正しく並ぶ扉と灯り。扉の色が一つずつでも違えばまだ覚えやすいだろうに、ここにいる人達こそいつも迷っているのではないかと思うほど、続いているのは同じ空間だった。
壁伝いに歩いていけば大抵の場合は抜けられる。そんな法則を思い出しながら出口を目指していたはずなのに、気づけばいくつも階段を下りている。
窓がないので外がどうなっているのかも確かめられない。だからと言って、引き返す勇気はなかった。後ろを振り向いたら、もう帰れないような気がした。
「帰りたい、のに」
なぜそんなささやかな願いすら、叶えてくれないのだろう。帰るべき場所に帰りたい、願いはそれだけだというのに。
「……誰か」
誰か、来る。直感が警告を発した。レヴィーナは壁に凭れかかって息を潜め、耳を澄ます。
癇癪を起こした空山の獅子王に叩き起こされたような足音が聞こえてくる。それも、一人ではない。複数。
――自分を探しているのだと、レヴィーナはそう思った。
だって自分をここに連れてきたあの大きな人は言ったのだ。『この部屋から出たら自分達よりもずっと怖いお兄さん達が君を探すだろう』と。
言いつけを守ってあの部屋でじっとしていればよかった。少なくともあの人は悪い人ではなさそうだったから。
それに、あの大きな人はウェイブのことを知っているようだった。だからもしかしたら――こんな所でというのもとても変だと思うのだけれど――ウェイブに会わせてくれるかもしれなかったのに。
今更悔いたところでもうあの部屋に戻る道もわからない。足音は段々とこちらに近づいてきている。
レヴィーナは咄嗟に背後にある扉を開こうと手を伸ばした。鍵は開いている。まだ幸運は抱きしめてくれている。わずかに開いた隙間から滑り込むように中に入る。どうかこの扉を開けるためにやってくるのではありませんようにと、心の中で強く願った。
然したる間を置かずに、足音は部屋の前を通り過ぎていった。歩くほどゆっくりではない。走っている。一つ、二つ、三つ、四つ目になったところで数えるのをやめる。それよりも多い。
足音はすぐに聞こえなくなり、レヴィーナはほっと息を吐き出した。彼らを追いかけていけば出られたかもしれないが、それよりも先に自分が捕まるのは間違いないので、追いかけるという選択肢自体を思考の外に放り出す。
「……?」
部屋の中、ふと視界の片隅を掠めた光にレヴィーナは振り返った。机の上の硝子板に、浮かび上がる文字がある。見るべき者――部屋の主もいないのに、それはひどく忠実に従順に、与えられた仕事をこなしていた。
レヴィーナはそろそろと近づいて、硝子板に浮かび上がった文字を覗き込む。これよりももっと大きな物を最初の大きな人の部屋で見たから、その仕組みは何となく理解していた。
一つ一つに文字や数字が書かれた小さな鍵盤のようなものと、文字を映し出す硝子板でできている道具。それもただの硝子ではなく、青水晶か何か魔力を介する物質が使われているのだろう、魔術の仕掛けだ。
自分で打ち込んだ文字と、他の場所から打ち込まれた文字と、両方を映すことができるらしい。大きな人の部屋にあった大きな物には、地図のような物まで映っていた。内部の、他の場所にいる者と連絡を取り合うための道具だ。
レヴィーナはそこに浮かび上がったままの文字をじっと見つめた。
『――侵入者を速やかに排除せよ。
《深緑の庭》の名の下に。』
記された言葉の意味をすべてきちんと理解できたわけではなかったけれど、ああ、やはり自分を探しているのだとレヴィーナは何となく思った。どういう経緯でここに来たとしても、己が侵入者である事に変わりはない。続く文字に目を走らせる。
「……え……?」
現れた文字を読んで、声を上げ、また最初から読み始める。繰り返すこと数回。読むと言うよりも、文中のある単語を、食い入るように見つめる、数秒。
――追われているのは自分ではないと、切り替えるに足る十分な理由がその先にあった。
『総員に告ぐ。
侵入者は、金の髪に瑠璃色の瞳の長身の男。年は二十代後半程で、長剣を持ち、言語魔術と精霊魔術を扱う。
侵入者は現在第三研究所西館より中央棟付近を移動中。
《深緑の庭》の名の下に速やかに排除せよ――……』
はっきりと刻まれた『侵入者』の特徴に、レヴィーナはただ一人、思い当たる人がいた。
けれども、本当にそうなのだろうか。レヴィーナが知っているその人が、ここに、来ているのだろうか。
「ウェイブ……?」
思い当たるその人の名を口にして、レヴィーナは画面を覗き込む。
文字は嘘をつかない。この文字を書き込んだ人が嘘つきならばこの文字も嘘になってしまうけれど、悪戯や冗談で多くの人を動かそうとしているとは、考えにくい。
この文字は、多くの人に、『見つけてほしい誰か』を伝えようとしているもの。ならば――
「来てる、の?」
――彼が本当にここに来ているというのだろうか。自分をおびき出すための罠ではないのだろうか。
宝探しができるような場所ではない。たぶん魔物もいない。ウェイブがここに来た目的など、レヴィーナには『自分を探しに来た』以外に思いつかない。
「どこ……?」
どこにいるのだろう。それ以前に、『ここ』はどこなのだろう。
会いたいのに、会いに行けるのに、近くにいるはずなのに――どこに行けば会えるのかがわからない。
「ウェイブ……」
まるで神の名を呼ぶように、レヴィーナは彼の名を呼んだ。扉の向こうに人の気配がないことを確かめてから、部屋を出る。
どっちに行けば会えるのかわからなかったけれど、とにかく、どこかに行くしかなかった。
ここで待っていてもきっと会えないのだから、だとしたら――
迷うだけのわずかな間もいらなかった。レヴィーナは、先程部屋の前を通り過ぎた足音が去っていった方角に向けて、走り出した。
だから彼女は知らない。
ウェイブの来訪を告げる文章が流れたその先に続いていた、もう一つの文章を。
『――侵入者はもう一名。少女、もとい、白い綺麗な花が一輪。
発見次第、速やかにその身柄を確保せよ。
なお、その際、一切の傷を負わせることを禁ずる――……』
*
「……いいんですか、博士。こんなことしちゃって」
端末に滑らせた指はピアノを弾くように硝子板の上に文字を紡ぎ上げる。
クロードの声に、レオナルドは溜め息交じりの声で答えた。
「構わんさ、緊急事態だ。何、ウェイブ=クラウドはそう易々と死んだりせんよ。今はレヴィーナの命を守る方が先だろう」
いやそうじゃなくて――クロードは続けようとした言葉を飲み込んだ。いくら第三研究所の所長という肩書きがあるとは言え、本部の許可なしに通達など前代未聞である。時間が時間とは言え、ばれない保証はどこにもないのに。
自分がどんなに説得力のある言葉を並べようと、レオナルドのそれを覆すことなどできないとわかっているが、それでもクロードは少し考えて、言葉を探した。
「だって、
庭師とは、この《深緑の庭》の最高責任者のことである。すべてにおいて最高の権限を有し、逆らえば命がないとも言われる存在ではあるが、レオナルドは全く意に介さない様子で答えた。
「緊急事態だからな。それに――ウェイブ=クラウドの侵入を許した時点で俺達が許されるとも思えん。どう転ぼうと、俺達にもう明日はないかもしれん。覚悟はしておけ。これは、賭けだ」
無数の文字が並ぶ硝子板から目を離し、レオナルドは些か、不敵な笑みをクロードへと向けた。
「賭け……? さっきもそんなことを。――博士、もしかして……」
レオナルドの言葉にクロードは思い当たるものがあった。だが顔面が蒼白になる暇もなかった。
「そう、その『もしかして』だ。この夜が明けたら、《深緑の庭》の歴史が変わるだろう。表向きには何も変わらなくとも、確かに、変わる。少なくともこれから変えるつもりでいるからな」
「博士――」
「『あれ』は、アムスの息吹の届かない存在だ。だからエルクの元に還す。それでいい。上の連中もこれで頭が冷えるかもしれないと思えば、俺達がこれからやることに意義はある。そう思わないか」
そう、『あれ』は外に出してはいけないものだ。一刻も早く、在るべき場所に還さなければならない。
そのためだけに、この《庭》の中で息を潜め、来るべき時が来るのをずっと待っていたのだ。レオナルドは口の端にわずかな笑みを浮かべながら、さらに文字盤を叩いた。
「博士、それで博士に何かあったらどうするつもりなんですか」
心配でたっぷりと塗り固められたクロードの言葉も、レオナルドは意に介さない。くっと喉の奥で笑いを堪えるように唇を噛み締めてから、緩く息を吐き出した。
「その時はその時だ。何、俺はまだまだ死ぬ気はないし、お前さんを死なせるつもりもないよ。ウェイブ=クラウドやレヴィーナに関してもそうだ」
レオナルドが打ち込んだ文字が画面に映し出される。手書きのそれではない、とても無機質な光の線が言葉となって綴られて行く。
『――地上を覆い、地下へ繋がる根の道を開け。作戦は追って指示する』
その意図をクロードはすぐに察した。それはおおよそ、彼や彼の上司が想像した通りの展開になるだろうということに対する、理解でもあった。曖昧な笑みが口元に滲む。
「……皮肉なものですね、根元を壊すなんて」
「根底から建て直さなければ、直るものも直らんだろう。――行くぞ、クロード。俺達が見届けなければならん」
レオナルドは腰を上げると、壁に立てかけてあった銀の錫状を手に取り、クロードを連れて部屋を後にした。
地下を目指して駆けて行く。深く深い闇の向こうに。