だが、レヴィーナの力はそうではなかった。《黎明の羽》の持ち主は、失われた血を補い、欠損した肉体の再生を可能にする。生きてさえいれば、例えば腕が千切れてもそれを再生させることができるのだ。
この当時、ハイゼルセイド王国は軍事国家としてその勢力を拡大している最中であった。
人間を魔物に造り替えるという、ウェイブ=クラウドに言わせれば『くだらない』計画を立ち上げた者達の狙いの一つは、《黎明の羽》の持つ力を実験体となった人間達に植えつけることだった。《黎明の羽》の持つ再生能力を利用できないだろうかと考えたのである。
成功すれば、勝手に動いて簡単に死なない、骸の兵士ができ上がるかもしれない。
骸は、ただ動くだけだ。感情のある人間の兵よりも、駒としては扱い易い。
すべては結果の予測できない実験段階だった。だから結果に対する仮定はいくつもあった。
《黎明の羽》の力に触れただけで実験体が崩れ去ってしまうというのも、予想された結果の範疇だった。
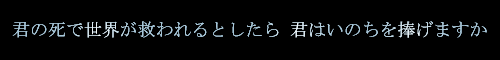
「――報告は以上です」
レオナルドはできる限りの厳かな声で告げると、己に向けられたいくつもの眼差しを挑むように受け止めた。漣のようなざわめきも意に返さない。その表情には一片の迷いも曇りもない。
騒ぎから一夜が明け、《深緑の庭》はそれすらもなかったかのような常の空気を取り戻していた。
一連の騒ぎを知っているのは、レオナルドとクロード、そして彼らの目の前に座る上層部の人間達だけだ。若い研究員や警備の者達には詳細までは伝えられておらず、だからこそ容易に日常を取り戻したのだと言っても、過言ではない。
「では、レオナルド博士。君が連れてきたという少女が《黎明の羽》であると、すぐに私に報告しなかった理由は?」
「言い訳がましいとは思われますが、報告をしようと準備をしていた矢先の出来事でした。そして彼女がそうであると、確かめる前に掻っ攫われました。《黎明の羽》だとはっきりわかったのは、実物をこの目で見たからです。それと……まあ、夜中だったので、
予め用意してあった原稿を読み上げるように淀みなく答えて肩を竦めたレオナルドに、老齢の庭師は少々面白くなさそうな顔をしながらも、それ以上を追求してくることはなかった。
「なるほど、《黎明の羽》も役に立たなかったということか」
その代わりのように苦々しく吐き捨てられた言葉にも、レオナルドはやはり冷静な態度を崩さないまま、真っ直ぐに庭師を見返した。
「少なくとも、役には立ちましたよ。《黎明の羽》の力が流用できないということがわかりました。結局、人間は人間にしかなれないということでしょう。その枠を外れた命までは、アムスの息吹の及ぶ所ではない……そうではありませんか?」
「君の言うことも尤もだな、レオナルド博士。ならば君はどう考える?」
レオナルドが押し黙った間はごくわずか。答えは最初から用意されていたかのように、整然と並べられていた。
「考えるまでもありませんね。計画そのものを廃止すべきかと思われますが、いかがでしょうか。コスト面を考えるだけでも、続けるにはリスクが大きすぎますし、それに……昨晩の騒ぎで少々、不安になっている兵達もいます。いつまでも隠し通せるとは……正直、思えません」
レオナルドは迷わずはっきりと、居並ぶ上層部の人間達を見渡しながら告げた。
長い沈黙があり、やがて庭師が深く息をついた。様々な感情を混ぜ込んで塗り固めた、重い溜め息だった。
「……やむを得ん、か」
その言葉を聞いた瞬間の、レオナルドの瞳の静かな輝きに込められた意味を、知っているのはクロードだけだ。
「では、博士。君自身の今後の進退について、我々はどう判断を下せば良いのかね?」
何気なく続けられた言葉にレオナルドは大きく目を見開いた。予想すらしていなかったらしい。驚きを隠せぬまま、半ば呆気に取られたように目の前の庭師を見つめていたが、やがて、笑いながらゆっくりと息を吐き出した。
「……それを俺自身に聞きますか、マスタ、貴方という方は。……そうですね、《黎明の羽》を掻っ攫った侵入者を逃がした責任を、取るつもりです。今この時をもって、《深緑の庭》における、フェライーダ・エルネスト・レオナルドが持つすべての権限を《深緑の庭》に返上致します。早い話が、俺をクビにして追い出して頂きたい。俺が望むのはそれだけです」
はっきりと言い放ったレオナルドに、庭師は白く長い髭の向こうで苦く笑った。
「そうか、君ほどの研究者を失うのは我々としても惜しいが、仕方あるまい。クレイクライン、君は?」
「――ぼ、僕は……マスタのお許しさえ頂けるのなら、レオナルド博士と共に、参ります」
いきなり話を振られてクロードは一瞬うろたえたものの、彼もまた、迷うことなくはっきりと答えを口にした。揺るぎない決意を感じ取ったのか、庭師は彼らを引き止める言葉を探そうとはしなかった。
「レオナルド博士、では、最後に一つ聞かせてくれ。……侵入者の正体については全くわからなかったのかね?」
君ほどの男が――と、その瞳は語っていた。レオナルドはわざとらしく肩を竦めて、笑った。
「はい、凄腕の剣士という印象ばかりが強烈に焼きついて、名前を聞く暇もありませんでしたよ。ああ、でも、俺の方がいい男です」
*
「……本当は堂々と外に出たかっただけですよね、博士」
会議を終えて、二人が《庭》を後にするまでにそれほど時間はかからなかった。街へと続く道を辿りながら、クロードは不意に口を開いた。
「それは言わない約束だろう、クロード」
まるでレオナルドの心中を代弁してくれているかのような、晴れた空だった。雲はなく、燦燦と光を放つ天球の姿が、地上からでも良く見える。
レオナルドの荷物は少なかった。小さな背負い鞄が一つ、それだけである。反対にクロードのほうが大荷物だった。両手で抱えるくらいの大きさの鞄が二つに、背負い鞄が一つ。要は、レオナルドの荷物までクロードの荷物の中に入っているわけなのだが、クロードは全く重そうな素振りを見せずに歩いていた。
「あんなに大見得切って飛び出してきちゃって、本当に良かったんですか、博士」
「構わんよ、未練はないさ。俺としてはクロード、お前さんのほうこそ良かったのかと聞きたいところだが、その辺はどうなんだ」
「それは……だって、僕がいないと何もできないでしょう、貴方は。食事の用意から何から、誰がやってたと思ってるんですか」
レオナルドは一瞬面食らったような顔をし、それから、どこか遠くを見つめて呟いた。
「お前さんが女だったら嫁に来いと言うところだろうがなあ」
まるで棒読みのその台詞に、クロードもまた、レオナルドから視線を逸らすように遠くを見た。
「……笑えないんで勘弁して下さい、さすがに」
こちらは切実な声音だった。
「……そうだな」
穏やかな風が吹いていた。
「ところで、博士、これからどこに行くんですか?」
吹く風の生温さに居た堪れなくなったらしい。クロードは無理矢理話題を逸らそうと乾いた笑みを顔中に貼り付けた。
「宛てはないさ。何、たまにはそういうのも悪くないだろう……そう言えば」
何かを思い出したらしく、レオナルドは懐を探り、小さな耳飾りを取り出した。淡い水色の宝石のついたそれに、クロードは思わず声を上げる。
「博士、それは……!」
「うむ、ウェイブの物だな。返しそびれただけだが、ちょうどいい。ウェイブ=クラウド――いや、夜明けの姫君を掻っ攫った侵入者を追いかけるとしよう。元よりそのつもりだったしな。運が良ければまだ追いつけるかもしれん、急ぐぞ」
早足が駆け足に変わり、その勢いが急速に失われるのもすぐのこと。
空は晴天、西の追い風を背に受けて、船は大海へと繰り出して行く。
歴史の裏舞台で繰り広げられたささやかな物語が、ひとつ、始まって終わりを告げた。
*
史実には、こう記されている。
これより数年後、ハイゼルセイド王国は圧政に苦しむ人々の手により国王が討たれ、共和制へと移行する。
それに伴い、王立の学術研究機関であった《
その二代目のギルドマスターとして、クロード・クレイクラインの名が残されている。
また、フェライーダ・E・レオナルドに関しても、ギルドとしての《深緑の庭》の歴史にこそ名は残されていないが、彼が後の世に遺した数百にものぼる書物から、その名を知ることができる。
そして、ウェイブ=クラウドとレヴィーナ=フローレントの足跡については――
二人の名はどこにも残されていない。彼らの足跡は歴史の知るところではないが、東方のティリンス王国に、光の翼を持つ少女と一人の騎士の物語が語り継がれている。
『アルゴス平原に突如として現れた《混沌》の使者の数は万を越え、無数の血色の瞳が王宮を射抜こうとしていた。
騎士達は一人、また一人と平原に屍を預け、残された人々の祈りは《光》には届かず、その祈りすら《混沌》に飲み込まれようとしていたその時、彼らは現れたのだ。
光の翼を持つ少女と、一人の騎士である。
二人がどこからやってきたのかは誰も知らない。
だが、彼らの出現と共に、ティリンスの騎士達はその心に《光》を取り戻した。
戦場を駆ける二人の姿は、さながら《光》の御遣いのようであったと、騎士達は口々に語った。
最後の夜が明けた時、戦場に立っていたのは《混沌》の使者ではなく、人間達だった。
そこに、夜明けをもたらす光があった――』と。
Fin.