いずれにしても清潔感に満ちている白一色の無機質な空間に、寝心地はさほど悪くないベッドと、主に食事を摂る時に用いられる丸いテーブルに椅子、この部屋の主だと言った男が暇潰し用にと置いていった何冊かの本――どれも暇潰し以前に内容が難しすぎて読めなかったのだが――が無造作に詰め込まれた本棚が鎮座している、そこはそんな部屋だった。壁を一枚隔てたもう一つの部屋では、身体を洗ったり用を足したりすることができる。
レヴィーナは好奇心一杯の翡翠の瞳を部屋のあちこちに向けていたが、何を何度見ても決して飽きることはなかった。想像の翼を広げるだけで、暇だと思う間もなく時は過ぎていく。
また、囚人と言っても、その待遇は考えるまでもなく恵まれすぎていた。屋根の下にいられるだけでも十分なのに、温かい食事と眠る場所までついている。少なくとも、彼女が暮らしていた街の牢屋はこんなに綺麗なものではないし、鉄と錆と汚物の匂いが充満している。何度も入れられた経験のある者はこれも慣れだと言ったけれど、あんな所に一週間でもいたら、そのきつすぎる匂いのせいで死ぬことだってできそうだった。
囚われのお姫様なんて気取っている場合ではないし、そんなつもりも毛頭ない。綺麗なドレスもきらきらと光るティアラも、彼女は持っていない。
けれど、今の彼女が置かれている状況を簡潔に表すならば、やはり『囚われのお姫様』というのが相応しいのかもしれなかった。レヴィーナにとってさほど大きな問題ではなかったとしても。
彼女にとってはどうでもいいことが、他の人にとってはどうでもいいことではないらしい。そうやって人と人は何らかの関わりを持つのだ。愛し合うこともできれば、傷つけ合うことだって容易く――どうして争うことばかりに熱中してしまうのだろう。皆が皆を愛することができれば、寒さに震える子供もいなくなるだろうし、あの牢屋に誰かが入る必要だってないのに。
レヴィーナはベッドから降り立つと隣の部屋に向かい、鏡の前に立った。着ていた服――白いローブのようなそれ――を脱ぎ、顕わになった背中を晒す。
彼女にとってはその『どうでもいいこと』の一つに過ぎなかった背中の――肩甲骨の辺りにある青い『痣』のような痕。生まれた時からあったものらしい、小さな翼にも見えるそれは、このフィルタリアという世界に於いてはとても珍しい、滅びてしまったとも言われている種族が持つ特徴に近いのだそうだ。
だからこそ、その種族のものであるかどうかを見極めるために、彼女は莫大な身代金と引き換えにこの《深緑の庭》へと連れてこられた。自分をここに連れてきた人とこの部屋の主は違う人で、この部屋の主は、自分をここに連れてきた人の『上司』で『責任者』だと言った。
レヴィーナをここに連れてきた人は、彼女が来なければ怖い人がウェイブを苛めると言った。苛められて、きっと牢屋に入れられてしまう。あんな所にウェイブが入るのはとても辛いだろうからと、レヴィーナはここに来ることを承諾したのだが――ウェイブにちゃんと行き先を告げられなかったのを今になって後悔している。さよならの挨拶だって言えなかったのだ。
レヴィーナと引き換えにあの家に残っているのは、大きな箱だ。その中にはたくさんのお金――それこそ、一生遊んで暮らせるような途方もない額のお金が入っているはずだ。レヴィーナのような不思議な『痣』を持つ人にかけられている賞金の額ということだった。
でも、きっとウェイブは要らないと言うだろう。彼が欲していたのはただ平穏でささやかな生活だ。そのために必要な物と言ったら、屋根のある家と最低限のお金――たぶんそれだけでいい。あんなにたくさんのお金は要らない。
それに、あんなにたくさんのお金を貰ったって、ウェイブもレヴィーナも――二人でも使い切れるかどうかわからない。
――神様って、本当に意地悪。
神は、人が心から欲するものを与えてはくれない。何をどう勘違いしているのか、その代わりに要らない物を強引に押し付けていく。
でも、神様にとってはきっと、ちょっとした悪戯に過ぎないのだろう。あるいは、願いは願うだけでは叶わないという、当たり前すぎて忘れてしまいそうになる――ほんの些細な戒め。
要らないと言ってはいけないのかもしれない。どんなに望んでいなくても、神が与え給うた物ならば。
さよならをしてこなかったことを、ウェイブは怒るだろうか。それとも、気にせずにあのお金を受け取るだろうか。
ウェイブにとって幸せならばそれでいいと思ったけれど――ちゃんとお別れの挨拶をするために、もう一度ウェイブに会いたいと思った。
――彼に会うためには、ここから出なければならない。
レヴィーナは、彼女がこの部屋に入る時に一度だけ潜った扉が、外へ――彼女のいた世界へと繋がっていることを知っていた。それが、彼女の力では開かないことも、また。牢屋のように、鍵がなければ扉は開かない。
それでも開けるしかなかった。動かないで誰かが助けてくれるのを待つよりは、どんなに痛い目に遭ったって自分で開けるほうがまだましだ。少なくとも、自分はそうやって生きてきたはずなのだから。
待ち続けていたって《
ここでじっとしていても、西の方角がどちらにあるのか、わからないのだ。
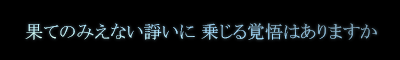
剣の交わる甲高い音と叫び声が、先程まで静寂を抱いていた《庭》に響き渡った。
ウェイブは軽く舌を打ちながら、その切っ先を翻す。白い石畳に広がる赤い色と鼻を突く血の匂いにかすかに眉を寄せたが――斬り伏せた兵士達に心を傾けている余裕はなかった。
「ここを通せ。二度は言わない」
そんな言葉が通じるならば、そもそも剣を振り翳す必要もない。息を呑み、動きを止める者は何人かいたけれど、瞬く間のことに過ぎなかった。
向けられる刃は凍えるような鋭さに満ちていて、言葉が入り込むわずかな隙間も初めからなかったかのように塞がれている。
彼らは――侵入者をそう容易く見逃せとは、教えられていない。寧ろ迅速に排除されるべきは他でもない己なのだから、侵入者たる自分に剣を向けることを彼らが躊躇う理由はどこにもない。
ざっと見渡しただけでも、十数人。いずれもかなりの手練であると、一目でわかった。言うなれば、それほどの実力がなければこの地の警備という役を担うことはできないのだ。
――『ここ』は、そういう場所だ。ウェイブはそれを知っている。
「う、うわあああああああっ!」
張り巡らされていた見えない糸を切ったのは誰だったか、最初の一人が威勢と剣を振るったのを皮切りに、その十数人が一斉に踊りかかってきた。
だが、ウェイブにしてみればこんな所で足止めを食らっている暇もなかった。緩く息を吐き出しながら、手にしていた剣を真横に傾ける。閉ざされた庭とは言え、風は吹き、何よりも彼が踏みしめているのは《フィリア・ラーラ》たる大地の欠片そのものだ。申し分はない。
「《空を駆ける車輪よ、その咆哮を以て我が道を拓け》――!」
ウェイブは構えていた剣を大きく振り払った。風の流れを刃が捉え、そこに魔力が絡みつく。同時に生まれた――文字通り空を駆ける咆哮のような音が、ウェイブへ襲い掛かろうとしていた兵士達を痛烈に薙いで吹き飛ばした。まるですべてを拒むような風が、砂埃と兵士達の苦悶に満ちた声を拾い、闇の中に溶けて消えた。
その風を追いかけるように、ウェイブは足を踏み出した。追いかけてくる者は誰もいない。ただ己に向けられたいくつもの眼差しに、宿り始めた戦慄の色を感じた。
振り返れば先ほど己が越えたばかりの石壁。進むべき道の先、それ自体が広大な迷宮にもなり得る《深緑の庭》の内部へと続く扉。その向こうに出口がなかったとしても、彼はそこへ乗り込んでいかなければならない。
空高く揺らめく雲が、月と星の光を覆いつつあった。夜明けまではまだ遠いが、時は着々とその足を進めている。
いつしか走り出していた足が大理石の階段を昇っていく。目の前に現れた《庭》への入り口は、豊穣の葡萄の蔓で縁取られ、花を咲かせた白亜の扉。 この《深緑の庭》に咲く知識の花がいつまでも枯れないようにとの意味合いが込められているらしいそれを、ウェイブはどこか複雑な表情で見やった。
長い年月を経る内に、淀んでしまった土で咲いた知識の花は、果たしてどのような色をしているのだろう。少なくともあの、選ばれた者だけが持つことを許される藍玉のように澄んだ色ではないだろうと、要らぬことを考えてウェイブは小さく頭を振った。
その扉には鍵がかかっているけれど、鍵穴がどこにもない。
扉を開けられるのはごく一部の限られた者、それもほとんどがこの《庭》に暮らす研究員達で、外部からの侵入者に過ぎないウェイブには、どう足掻いても鍵を手にすることはできないのだ。
開かないのなら開ければいい。そんな単純な話で済むのなら当の昔にここは滅んでいるだろうが、それでもこじ開けるつもりでウェイブは扉に手を触れた。
「……?」
扉に絡みついた蔦が光を帯びて、鍵が外れたような音がする。
まるで悪戯な風の気紛れが降り注いだかのように、扉は開いていた。
「――罠か?」
こんな夜更けに訪れる者の目的など容易に知れているだろうに、《深緑の庭》は侵入者を受け入れるというのか。
ウェイブにとって扉が開いたことは寧ろ好都合だったが、その先に待ち受けているのは敵しかいない。
「否……」
呟いて、思い直す。
待ち受けているのは大勢の敵と救うべき少女と、腐れ縁の続くどこかの『博士』だ。
《